ユーザーの声で進化する語彙アプリTANZAM──CTOが語る、開発のリアルと柔軟なチームづくり
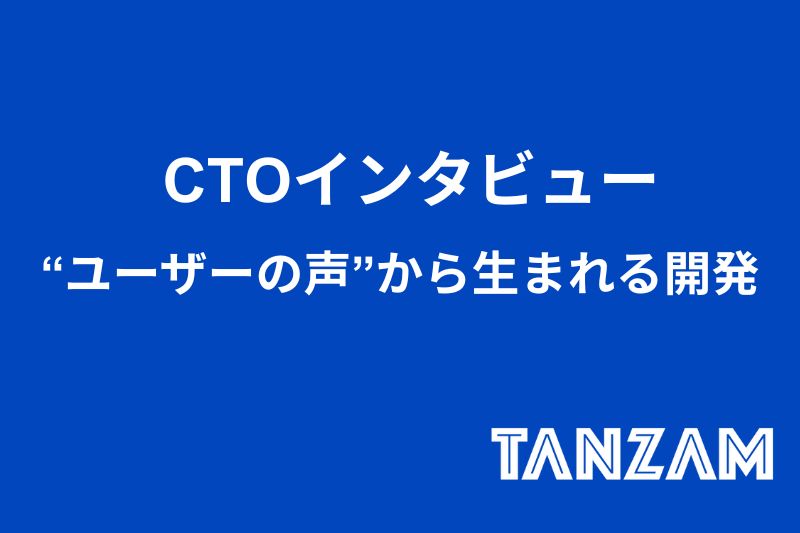
ユーザーの声が、すぐにチームに届き、次の改善につながる。
エンジニア自身が“自分ごと”で技術を選び、手を動かす。
メンバーの提案が、自然とチーム全体のものとして形になっていく。
そんな、オープンで柔軟なプロダクト開発の現場が、TANZAMにはあります。
TANZAMは、急成長を追い求めるのではなく、ユーザー一人ひとりとの対話を大切にしながら、少しずつ価値を積み上げてきたプロダクトです。
CTOの竹林佑斗さんは、創業期から現在に至るまで、フルリモート・少人数・パートナーシップ型の開発体制の中で、プロダクトとチームを丁寧に育ててきました。
本記事では、竹林さんが語る「TANZAMの開発現場のリアル」と、「どんなエンジニアと働きたいか」というメッセージを通じて、TANZAMの開発哲学とチーム文化の魅力をお伝えします。
CTO竹林佑斗の自己紹介とTANZAMとの出会い
TANZAMの開発をリードするCTO・竹林佑斗さんは、もともと自然言語処理やDeep Leraningを専門とするエンジニアです。
大学では自然言語処理を学び、卒業後も機械翻訳の技術に関わる業務に従事してきました。
言語そのものの構造や意味に向き合ってきた経験が、現在のTANZAM開発にも深く活かされています。
そんな竹林さんがTANZAMと出会ったのは、あるエンジニア紹介サービスを通じてでした。
当時は別の企業に所属しながら、週末や空き時間を活用してプロジェクトベースで開発に関わるパラレルキャリアを歩んでいた時期。
TANZAMの開発依頼を見たとき、「自分が作りたいと思えるアプリだ」と直感したといいます。
TANZAMの特徴は、「視覚で覚える」という語彙学習のコンセプトにあります。
竹林さん自身も手で書いて覚えるタイプの学習者であり、視覚的に印象を残す学習体験に強く共感していました。
そのため、このプロダクトの方向性は、自身の興味や経験とも深くフィットしていたと語ります。
「言語が好きで、自然言語処理もやってきた。さらにアプリも作りたいと思っていた。その3つがうまく重なっていたのがTANZAMでした」
開発者としての関心と、言語への探究心。その両方を満たすTANZAMとの出会いは、まさに偶然のようで必然だったのかもしれません。
開発初期の苦労とやりがい
TANZAMの開発初期は、明確な仕様や設計書がほとんどない状態からのスタートでした。
必要とされている機能の方向性はあるものの、具体的な項目やデータ構造までは詰められておらず、まさにゼロイチでつくりあげていくフェーズ。
当然、最初から正解があるわけではなく、試行錯誤の連続でした。
竹林さんは当時を振り返り、「最初に取り組んだのが、データベース設計だった」と語ります。
各項目が何のために存在するのか、どのように使われるのかをひとつずつ確認しながら、「使わないなら削った方がいい」と開発目線で提案する場面も多かったといいます。
そうした対話の積み重ねを通じて、プロダクトの輪郭が少しずつ見えていきました。
実はこの時期、チームメンバーそれぞれが限られた時間とリソースの中で開発に携わっていたという背景もあります。
子どもが生まれたばかりのメンバー、本業と並行して副業的に関わっていたメンバーなど、全員がフルタイムではない状況。
だからこそ、「本当に必要なことだけに集中する」という視点が、ごく自然に育まれていきました。
生活と開発のバランスを取りながら、「どんな機能が本当に必要か」「時間をかけてでも残すべき価値は何か」を粘り強く見極めていく日々。
その問いかけが、TANZAMにとって“意味のある機能”を選び抜く基準になっていったのです。
そんな制約の中でも、前に進めた最大の理由は、共同創業者間での密なコミュニケーションにありました。
仕様の背景や意図を聞き出し、開発に落とし込む。
ときには数時間にわたって議論を重ねながら、一緒に形にしていく。
「一緒につくっている」という共創の感覚が、ゼロイチのフェーズを支えていました。
「1からすべて作るのは大変でしたが、そのぶん“自分で考えて組み上げた”という手応えは大きかったです。仕様を言語化していくプロセスも含めて、すごく鍛えられたなと感じています」
設計と実装を同時に走らせながら、チームとともに“意味のある機能”を探っていく。
そんな開発初期の経験が、TANZAMの根幹にある柔軟でオープンな開発文化を育てていきました。
TANZANチームの進化と成長
TANZAMの開発チームは、CTOである竹林さん1名から始まりました。
そこに外注パートナーが加わる形で、少しずつ拡張されていきます。
現在は、日本人PMとオフショアエンジニア(主にベトナム)を中心とした外注チームが構築され、プロダクト開発の中核を担っています。
この体制の特徴は、単なる「外注」ではなく“パートナー”としての関係性を重視していることです。
仕様や設計を一方的に渡すのではなく、プロダクトの思想や改善の意図をしっかり共有することで、チームの一体感を醸成してきました。
とはいえ、はじめからスムーズだったわけではありません。
特に初期は、設計の意図や背景が伝わらず、「なぜこの仕様になるのか」が伝わりにくい場面も多くあったといいます。
その壁を乗り越えるきっかけとなったのが、オフラインでの対面機会でした。
「実際に外注メンバーに会いに行って、食事をして、顔を合わせて仕事をしたことで、一気に距離が縮まりました。お互いの温度感が伝わるようになり、コミュニケーションも格段に円滑になりました」
今では外注メンバーから「この仕様はこうした方がいいのでは?」といった提案が出てくることも珍しくありません。
竹林さんは、「もはやTANZAMの一員として動いてくれている」と感じており、その関係性は実際のチームメンバーと変わらないものになっています。
役割や契約形態を超えて、同じ目的に向かって動く仲間としての信頼。
TANZAMの開発チームには、“外注なのに仲間”という理想的な関係性が、自然と築かれているのです。
技術裁量とプロダクト思想
TANZAMの開発チームには、トップダウンではない“現場起点”の意思決定が根づいています。
どんな技術を使うか、どうやって機能を実装するか──こうした選択の多くは、開発チーム自身に委ねられています。
「やりたい技術があれば、まず試してみる。提案に“誰が言ったか”は関係なく、“なぜそれが必要か”で判断する」。
竹林さんはそう語ります。
これは、社内・外注の区別なく、どのメンバーからでも提案できる空気があるということ。
立場や経験年数に関係なく、良いと思うことは自由に発信できるチーム文化が、プロダクトの柔軟性と進化を支えています。
その自由の中で、竹林さん自身が注目しているのが自然言語処理や大規模言語モデル(LLM)の応用です。
たとえば、TANZAMでは単語の4択クイズを提供していますが、そこに出てくる「ダミー選択肢」にも意味を持たせたいと考えています。
こうした発想は、単なる「機能追加」ではなく、学習体験そのものの質を上げる工夫です。
技術はあくまで手段であり、「なぜそれをやるのか」という目的から始まるのがTANZAMの開発スタイル。
プロダクトの根底には、「楽しく、効率的に、言葉を覚えてほしい」という一貫した思想があります。
技術に裁量があるだけでなく、その技術が“誰のためにあるか”を問い直せる場所。
TANZAMの開発チームは、まさにそんなプロダクトづくりの現場です。
エンジニアにとっての“働きがい”
TANZAMの開発チームには、エンジニアがやりがいを感じられる要素がいくつもあります。そのひとつが、「裁量」と「反応の速さ」が両立していることです。
TANZAMでは、エンジニアが実装をリードし、提案した内容がすぐに採用され、すぐにユーザーの反応として返ってくる。
機能をリリースした翌日に、「これ、すごく使いやすくなりました!」というレビューが届くことも珍しくありません。
「作ったものに対して、短期間でリアルなフィードバックが返ってくる。このスピード感は、他のプロダクトではなかなか味わえない感覚です」
竹林さんは、そうした“つくる喜び”が自然とエンジニアのモチベーションにつながっていると語ります。
誰かに言われたから作るのではなく、「ユーザーの反応が見たいから作る」。TANZAMの開発には、そんな実感があります。
もうひとつの魅力は、副業やパラレルキャリアとの相性の良さです。
TANZAMの開発は基本的にリモートかつ非同期で進行しており、働く時間や場所に縛りはありません。
実際、竹林さん自身も他社での仕事と両立しながら長年プロダクトに関わってきました。
「夜にミーティングをして、日中は自分の仕事をする。そんな柔軟なスタイルが自然と根づいています」
時間的にも心理的にも余白があるからこそ、自律的に動けるチームになっている。
TANZAMの開発現場には、“信頼に基づいた自由”が確かに存在しています。
どんな人と働きたいか
TANZAMでは、特定のスキルやフレームワークに縛られた募集はしていません。
それよりも大切にしているのは、「どんな想いでプロダクトに向き合えるか」という姿勢です。
竹林さんが一緒に働きたいと語るのは、次のようなエンジニアです。
英語や言語学習に興味がある人
TANZAMは、語彙学習を支援する言語アプリです。
もちろん開発そのものがメインの仕事ですが、背景にある「ことば」や「学び」に関心を持っている人のほうが、やはりフィットします。
「海外が好き、英語が好き、語学が好き。そんな気持ちがあると、自然とプロダクトの細部にも目が届くと思います」
自分発信で動ける人
TANZAMの開発現場には、細かい指示やルールがあるわけではありません。だからこそ、「これをやりたい」「こうした方がいい」と、自分から提案・実行できる人が活躍しています。
「自分からどんどん動いていける人がTANZAMには合っていると思います。
指示を待っているだけだと、正直、外注とあまり変わらない。むしろ外注メンバーでも積極的に提案してくれる方が多いので、自分で考えて動けることが、チームの中でより大きな価値につながると思います」
“ユーザーが喜ぶ”ことにワクワクできる人
TANZAMの開発では、ユーザーの声が驚くほど近くにあります。
「このUI、もっとよくできそう」「このフロー、少しでも分かりやすくしたい」。そんな視点を持って、ユーザー視点で工夫できる人を歓迎しています。
「機能を作ることが目的じゃなくて、使われて喜ばれることがゴール。その感覚に共感できる人と、一緒に開発していきたいです」
CTOからのメッセージ
TANZAMの開発を通じて、竹林さんが一貫して大切にしていることがあります。
それは、「技術を目的にしない」という姿勢です。
「新しい技術を使いたいから導入する、というよりも、“どうすればユーザーにとってより良い体験になるか”を起点に技術を選びたいと思っています」
目的が先にあって、その達成のために最適な技術を選ぶ。
そんなシンプルだけれどぶれない姿勢が、TANZAMの開発チームには根づいています。
TANZAMは決して爆発的に成長してきたプロダクトではありません。
しかし、一つひとつの機能が、ユーザーとの対話の中で丁寧に磨かれてきたという誇りがあります。
リリース後も、レビューやSNS、直接の問い合わせを通じて、たくさんの声が届き続けています。
「ユーザーが自然と語ってくれるプロダクトって、そんなに多くないと思うんです。TANZAMは、まさにそういう存在だと思っています」
開発チームとしても、常に進化の途中です。使いやすさを追求するUI改善も、自然言語処理を活かした新機能も、まだまだ伸びしろがたくさんあります。
そしてその先には、覚えた英語が誰かとの会話につながったり、新しい世界に一歩踏み出すきっかけになるような、「学びのその先」まで支えられるプロダクトを目指しています。
そんなTANZAMの未来を、一緒に作ってくれる仲間を探しています。
