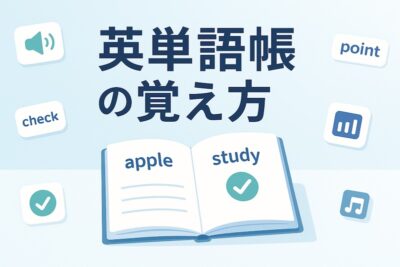大学受験の英単語の覚え方|科学的に覚える勉強法とおすすめアプリ

「毎日単語帳を見ているのに覚えられない」
「何度やっても同じ単語を忘れてしまう」
そんな悩みを抱える受験生は少なくありません。
努力が報われない原因は、覚える量よりも“覚え方”にあります。
英単語は、読解・英作文・リスニングなど、英語力すべての土台です。
単語を知らなければ、どんなに文法ができても内容を正確に理解できません。
ただし大切なのは、単語の“量”ではなく“質”。
市販の単語帳を丸暗記するより、共通テスト頻出の「高頻度語」や志望校で出やすい「中頻度語」を効率よく覚える方が、得点に直結します。
このあと紹介する方法では、単語を「覚える」だけでなく「使える知識」に変えるための理論と実践法を解説します。
科学的根拠に基づく英単語暗記理論
英単語の暗記は「根性」ではなく「科学」です。
ここでは、記憶研究や教育心理学に基づいた5つの理論をもとに、“効率よく・忘れにくい”覚え方を整理します。
忘却曲線と間隔反復(SRS)
人の記憶は、時間とともに急速に薄れていきます。
これは心理学者エビングハウスの「忘却曲線」で知られています。
この忘却を防ぐために有効なのが、間隔反復学習(Spaced Repetition)。忘れかけたタイミングで復習を行うことで、記憶が長期的に定着します。
効果的な復習タイミングは、
1日後 → 3日後 → 7日後 → 14日後 → 1か月後。
この周期を自動で管理できるのが、TANZAMのようなSRS(間隔反復システム)です。
また、紙の単語カードで同様の効果を出す方法がライトナー方式(抽認箱法)。
覚えた単語は復習間隔を伸ばし、間違えた単語はすぐ復習するという仕組みです。
これをデジタルで効率化したのが現代の学習アプリです。
再生練習(Retrieval Practice)
「何度も読む」より「一度思い出す」ほうが記憶に残る。
これは教育心理学で実証された再生練習(テスト効果)という現象です。
STUDY HACKERの紹介でも示されているように、人は情報を“取り出す”行為そのものによって記憶を強化します。
つまり、ただ眺めるより、小テスト形式で思い出す練習をした方がはるかに効果的なのです。
さらに重要なのが誤答学習(エラーフィードバック)。
間違えた単語こそ記憶を再構築するチャンス。
間違いを放置せず、「なぜ違ったのか」を意識して復習すると、次に忘れにくくなります。
二重符号化(Dual Coding)
記憶は「文字」だけでなく、「音」や「イメージ」と結びつくほど強くなります。
この仕組みを利用したのが二重符号化理論(Dual Coding)。
たとえば、単語の発音音声を聞きながらスペルを見たり、語源やイラストと結びつけて覚えたりすることで、脳内で複数の経路が作られ、思い出しやすくなります。
レアジョブ英会話のように音声+テキスト学習を組み合わせたスタイルが効果的な理由もここにあります。
英単語アプリでも、音声・画像・例文を同時に提示する設計がこの理論を応用しています。
インターリービング(混合学習)
多くの人は「今日は形容詞」「明日は名詞」と分類して覚えようとしますが、実はあえて混ぜる方が効率的です。
同じジャンルばかりを固めて学ぶ“ブロック学習”に比べ、異なるジャンルを交互に学ぶ“混合学習(インターリービング)”では、語の使い分け力や理解の深さが高まることが研究で分かっています。
たとえば「increase」「improve」「enhance」のような類義語を一緒に学ぶと、微妙なニュアンスの差を自然に整理できるのです。
モチベーション理論・間違い学習(エラー駆動型学習)
ウォール・ストリート・ジャーナルの記事でも紹介されているように、間違いは記憶を深める最高のトリガーです。
「間違えてはいけない」と思うほど学習は受動的になります。
むしろ、間違いを分析し、どうすれば正答できたかを考える“エラー駆動型学習”が、学習効率を大きく高めます。
また、勉強のモチベーションを保つには、小さな達成の積み重ねが重要です。
学習量より「今日も続けられた」という感覚が、習慣化を支えます。
TANZAMのように進捗が可視化されるアプリは、この心理的効果をうまく利用していると言えるでしょう。
このように、英単語の暗記には確かな科学的裏付けがあります。
“努力を成果に変える仕組み”を理解して取り入れることで、勉強時間の効率も、記憶の定着率も大きく変わります。
短期〜中期〜本番まで使える実践プロトコル
理論を知っても、「具体的にどう進めればいいのか」が分からなければ成果にはつながりません。
ここでは、受験までの数か月を想定した実践プロトコルを紹介します。
短期・中期・本番直前の流れを整理し、毎日の学習を最も効率化する方法をまとめました。
目安量とスケジュール設計
英単語学習で重要なのは「1回で完璧に覚えようとしないこと」。
記憶は反復の中で強化されるため、以下の1・3・7・14日の復習テンプレートが基本となります。
| 日数 | 学習内容 | ポイント |
| 1日目 | 新出単語をインプット(50〜80語) | 発音・意味・例文をセットで確認 |
| 3日目 | 再生練習(クイズ形式で思い出す) | 間違えた語を抽出リストに登録 |
| 7日目 | まとめ復習(全体の理解確認) | 意味・発音・文中使用を再確認 |
| 14日目 | 総復習+新出語追加 | 「忘却防止+知識拡張」の両立 |
これを1サイクルとして回すことで、短期間で定着率が急上昇します。
また、受験までの残り期間で次のように逆算して計画を立てるのが理想です。
3か月前:基礎語彙の網羅(高頻度語中心/1日50〜80語)
1か月前:中頻度語・出題傾向語を集中強化(苦手分野を重点的に)
1週間前:総復習+誤答ノート確認/発音・意味の最終チェック
「1日80語 × 3か月」でおよそ7,000語に到達可能。
ただし、覚えるより“復習サイクルを守る”ことが最優先です。
テスト形式演習+誤答処理ルーチン
英単語学習の中心は「テスト形式」。
読むだけではなく、“思い出す練習”を必ず取り入れましょう。
効果的なルーチン例:
- 小テストを実施(アプリまたは単語帳の隠し部分で)
- 間違えた語を誤答カードへ登録
- その場で再テスト(30秒以内に思い出す)
- 復習リストに自動追加(抽選式で数日後に再出題)
これにより、「忘れやすい語ほど多く出てくる」状態を作れます。
これはライトナー方式と同じ仕組みで、“弱点に時間を集中させる”非常に効率的な学習法です。
例文+音声併用練習
単語を「意味」で覚えるだけでは、実際の長文で使えません。
定着を強化するには、例文・音声・発声の三段階を組み合わせましょう。
- 単語を読む:目でスペルと意味を確認
- 単語を聞く:音声を流して正しい発音とイントネーションを認識
- 単語を声に出す:発音しながら意味を思い浮かべる
この3ステップにより、「音」と「文脈」が記憶の中で結びつき、忘れにくくなります。
また、覚えた単語を使って自分で短い例文を作ることもおすすめです。
自作例文は“能動的記憶”を促し、英作文力の基礎にもなります。
モジュール混合学習(語彙 × 熟語 × 語法を交互に)
「今日は単語」「明日は熟語」と完全に分けてしまうより、あえて混ぜるほうが記憶は定着します。
たとえば、
- “put off(延期する)”を学んだあとに“delay”との違いを整理する
- “depend on”を学んだあとに“rely on”や“count on”をまとめて比較する
このように異なるカテゴリーを交互に扱う混合学習(インターリービング)は、応用力と識別力を高めます。
TANZAMの「関連語・類義語」データを活用すれば、この流れを自然に取り入れられます。
これらのプロトコルを組み合わせることで、単語学習は単なる暗記作業ではなく、「戦略的な記憶設計」になります。
理論に基づいた反復・再生・音声・比較を取り入れ、限られた時間で最大の成果を引き出す学び方を実践していきましょう。
単語帳・アプリ・教材の“賢い使い分け”戦略
英単語の学習ツールは「紙」も「アプリ」も数えきれないほどあります。
しかし、最も大事なのは「どれを使うか」ではなく、どのように使い分けるかです。
ここでは、受験生のレベル・目的・生活スタイルに合わせた最適な組み合わせ方を紹介します。
タイプ別おすすめツール比較
【紙の単語帳】
特徴:手を動かしながら覚えることで記憶が定着しやすく、自由に書き込みも可能。
向いている人:手書き派・ノート整理が得意な人。
注意点:復習間隔を自分で管理する必要がある。
【書き込み型単語帳】
特徴:発音記号や例文、派生語まで1冊で確認できる。
向いている人:視覚的に整理して覚えたい人。
注意点:ボリュームが多く、持ち運びには不向き。
【アプリ型】
特徴:音声再生・テスト機能・復習リマインド付きで、いつでもどこでも学習できる。
向いている人:通学中や休み時間など、隙間時間を活用したい人。
注意点:手を動かす刺激が少なく、スペルの定着には別途対策が必要。
【混合型(紙+アプリ連動)】
特徴:紙でインプットした単語をCSVなどでアプリに登録し、繰り返し復習できる。
向いている人:両方の良さを取り入れたい人。
注意点:最初に管理の仕組みを整える手間がある。
たとえば、共通テスト対策では「頻出語を短期間で繰り返せるアプリ型」がおすすめ。
一方で、難関大志望者は「紙+アプリの併用」で、中頻度・高難度語も体系的に整理すると効果的です。
ツール併用のコツ(紙+アプリで補完)
どんなツールにも得意・不得意があります。
そのため、紙とアプリの“役割分担”を意識すると定着率が格段に上がります。
おすすめの使い分けは以下の通り。
- 通学時間・休み時間 → アプリ学習
短時間で復習を回すのに最適。
TANZAMのようなSRS搭載アプリなら、記憶が薄れるタイミングで自動的に出題してくれます。
- 自宅の学習時間 → 紙の単語帳+ノート
紙に書きながら覚えることで、スペルや語法の記憶が強化されます。
特に、英作文や英語表現問題対策には「書く練習」が欠かせません。
- 週末・テスト前 → ノートでまとめチェック
一週間分の誤答や苦手単語をノートに整理。
例文や派生語を追加することで、「点」で覚えていた単語が「ネットワーク」でつながります。
このように「アプリ=回転」「紙=定着」「ノート=整理」と役割を分けると、どの学習法も活かせるようになります。
失敗・停滞しやすいパターンとその対処法
英単語の学習は「やり方」を間違えると、どんなに時間をかけても成果が出ません。
ここでは、受験生がよく陥る5つの落とし穴と、それを乗り越えるための具体的な方法を紹介します。
【1】書き写しだけで終わってしまう
ノートにひたすら単語と意味を書いて満足していませんか?
「書くこと」で一時的に覚えた気になっても、“思い出す練習”がないと記憶は定着しません。
対処法:書く練習から“テスト形式”に切り替える。
たとえば、「日本語を見て英単語を書く」「音声を聞いて意味を選ぶ」など、頭から引き出すトレーニングを中心にしましょう。
TANZAMのクイズ機能のように、出題形式で復習する仕組みを使うと、定着率が一気に上がります。
【2】覚えた気になって復習していない
「昨日やった単語は大丈夫」と思っても、1週間後には半分以上忘れてしまうこともあります。
これは自然なことで、悪い記憶力ではなく、“復習のタイミング”が合っていないだけです。
対処法:復習スケジュールを自動化する。
1・3・7・14日サイクルのように、間隔を空けて復習すると記憶が長期化します。
アプリのリマインド機能を活用すれば、「忘れそうな頃に出てくる」理想的な復習ペースを自動で維持できます。
【3】同義語が混ざって混乱する
“increase”と“improve”、“speak”と“talk”のように、似た意味の単語がごちゃ混ぜになって覚えづらい…というのもよくある悩みです。
対処法:混合学習(インターリービング)と対比例・語源分析を取り入れる。
たとえば、類義語を一緒に学んで違いを整理する。
“benefit(利益)”と“advantage(利点)”を同時に学ぶと、使い分けが自然に理解できます。
また、語源を確認すると意味のつながりが見え、単語が「つながって」記憶に残ります。
【4】継続できない・途中で飽きてしまう
最初の1週間は頑張れるのに、その後続かない…。
それは根性ではなく、「習慣化の仕組み」が足りないだけです。
対処法:学習を“仕組み”で続ける。
1日のノルマを「10分」「30語」と小さく設定し、終わったらチェックを付ける。
TANZAMのように学習記録が可視化される仕組みを使えば、「続けた自分が見える」ことがモチベーションになります。
人間は成果よりも“進捗の実感”で動く生き物。努力を見える化すれば、継続は自然と習慣になります。
【5】無理な量を設定して挫折する
「1日200語!」と決めても、2日目にはペースダウンしていませんか?
単語学習で最も大切なのは、“続けられる量で回すこと”です。
対処法:量ではなく“定着率”で設計する。
目標は「100語覚える」ではなく、「80%定着させる」。
単語学習で伸びる人は、「完璧な暗記」よりも「仕組みを整える」ことを優先しています。
覚え方やツールを工夫すれば、記憶力や集中力に関係なく、確実に結果はついてきます。
実例&成功ケース紹介
「単語をやっても覚えられない」「続かない」「すぐ忘れる」――そんな悩みを持つ受験生は少なくありません。
しかし、学習法を少し変えるだけで、記憶の定着や模試の点数は確実に変わります。
ここでは、実際に成果を出した3人のケースを紹介します。
【ケース1】高2の夏からスタートし、偏差値+10を達成
Aさん(国公立志望・高校2年)
英語の偏差値は52。単語帳を何周しても覚えられず、やる気が続かない時期がありました。
そこで始めたのが、「1日50語+自動復習アプリで管理」というシンプルな習慣。
朝に新出単語を確認し、夜はアプリの復習リマインドに従って再テスト。
3か月後には定着率が約8割に上がり、模試の英語偏差値は52→62へ。
「“いつ復習すればいいか”を考えなくなったら、気持ちが軽くなった」と話しています。
(使用アプリ:TANZAM)
【ケース2】浪人生・1日30分の習慣で語彙数+2,000
Bさん(私立文系志望・浪人生)
「暗記は苦手」「やる気が続かない」と感じていたBさん。
通学時間にスマホで単語学習、帰宅後にノートで“誤答だけ”を書き直す方法を採用しました。
朝10分・夜20分のルーティンを2か月続けた結果、語彙数は約3,800語→5,800語に増加。
「ノートで“自分が間違えた単語だけ”をまとめると、復習が早くなって苦手が減った」と実感。
紙とアプリを組み合わせた「ハイブリッド型」の成功例です。
(使用:紙の単語帳+市販アプリ)
【ケース3】共通テストのリスニングが40点→74点にアップ
Cさん(高3・共通テスト対策)
単語はある程度覚えていたものの、「聞き取れない」「発音が分からない」ことが悩み。
そこでTANZAMの音声例文機能を使い、単語ごとに“読む→聞く→発音する”の三段階で練習しました。
3か月後、模試のリスニング得点は40点→74点に上昇。
「意味と音をセットで覚えると、リスニングが一気に楽になる」との声も。
音声×例文の“二重符号化”をうまく活用した好例です。
まとめ・次のステップ
英単語学習は、才能や根性ではなく「仕組み」で結果が変わります。
書き写すだけの暗記から抜け出し、“思い出す練習”と“計画的な復習”を組み合わせることで、記憶は長期化し、点数は確実に伸びます。
この記事で紹介した通り、成果を出している受験生は次の3点を大切にしています。
- 忘却曲線に合わせて復習する(タイミング管理)
- 音声・例文を活用して「意味+音」で覚える
- 定着率で学習を測り、無理せず続ける
英単語学習の本質は「量」ではなく、「定着率 × 継続率」。
焦らず、自分のペースで“忘れにくい学び方”を積み上げていきましょう。