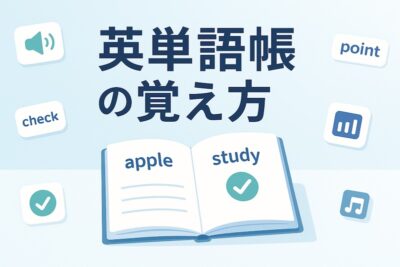英単語カードの作り方完全ガイド|覚えやすく続けられる勉強法と活用コツ

英単語カードを作り始めたけれど、気づけば続かなくなっていた——そんな経験はありませんか?
「せっかく書いたのに、次の日には忘れてしまう」
「作ることに時間がかかって、肝心の勉強が進まない」
など、英単語カードはうまく使えないと“作業”で終わってしまうことがあります。
けれど、それは努力不足ではなく、“作り方”の仕組みが合っていないだけです。
実は、カードの構成や使い方を少し工夫するだけで、記憶効率は驚くほど上がります。
この記事では、記憶のメカニズムに基づいた「覚えが定着する英単語カードの作り方」を、紙とアプリそれぞれの視点から紹介します。
あなたに合ったスタイルで、今日から「作る」ではなく「覚える」英単語カードに変えていきましょう。
結論ファースト|覚えやすい英単語カードの条件3つ
覚えやすい英単語カードには、共通した“設計の型”があります。
なんとなく書き写すよりも、「どうすれば思い出せるか」を意識して作ることがポイントです。
想起できる設計(表=ヒント、裏=答え)
表面には「単語そのもの」ではなく、“思い出すための手がかり”を入れましょう。
たとえば、「日本語訳だけ」ではなく、例文の一部を空欄にする、「語源ヒント」や「関連イメージ」を書くなど。
裏面には答え(英単語+発音+意味)を簡潔に。
目的は「見るためのノート」ではなく、「思い出すためのカード」にすることです。
感覚を使う(音声・イラスト・文脈を入れる)
人の記憶は、視覚・聴覚・文脈の情報が重なるほど強く残ります。
たとえば「apple」なら、リンゴの画像+音声+“I ate an apple.”という短文をセットに。
手書きカードでも、シンプルなイラストを添えるだけで記憶の引き出しが増えます。
アプリの場合は、音声再生・例文付きカードを活用するのが効果的です。
復習しやすい(順番シャッフル・苦手抽出)
作ったカードをただ順番通りに眺めるだけでは、定着しません。
「覚えているか」を確認できるように、順番をシャッフルしたり、苦手なカードだけを集めて復習する仕組みを作りましょう。
紙のカードなら、輪ゴムで“できた/まだ”に仕分け。アプリなら自動で苦手を抽出してくれます。
つまり、英単語カードを作る目的は“見ること”ではなく、“思い出すこと”。
この3つの条件を意識すれば、ただの暗記作業が、記憶を積み重ねる学習に変わります。
ステップ別|英単語カードの作り方
英単語カードを“作って終わり”にしないためには、ステップごとに目的を明確にすることが大切です。
ここでは、初心者でもすぐに実践できる、効果が長続きするカード作りの流れを紹介します。
ステップ1:単語を選ぶ —「量より質」でスタート
まずは、1枚=1単語を原則にしましょう。
いきなり100語作るよりも、毎日10〜15枚を着実に増やす方が効果的です。
最初に選ぶのは、
- 定期テスト・英検・TOEICなどでよく出る単語
- 何度見ても忘れる“苦手単語”
- 自分の興味ある分野(food, emotion, travelなど)
のいずれかに絞ると続けやすくなります。
テーマごとに輪ゴムで束ねておくと、復習時に関連語が一気に定着します。
ステップ2:表面を作る — 思い出すための「ヒント」を仕込む
英単語カードの表面は「思い出すための入口」です。
よくある「日本語=英語」だけの形式では、思考が止まりやすく、記憶も浅くなります。
そこでおすすめは、“文の一部を空欄にする”か、“イメージでヒントを与える”こと。
例:
- 「I ___ to school every day.(歩いて)」→ walk
- 「He is very ___ when he speaks in public.(緊張している)」→ nervous
- 絵カードの場合:小さなりんごの絵 → apple
このように、文脈や場面を想起させる構成にすると、テストで思い出すスピードも格段に上がります。
ステップ3:裏面を作る — 答え+発音+文脈をセットに
裏面には、ただ答えを書くのではなく、「発音+意味+文脈」をセットにしておくのがポイントです。
おすすめの構成:
- 単語:walk
- 発音記号:/wɔːk/
- 例文:I walk to school every day.
- 意味:歩く
- 音声(アプリなら自動再生)
紙の場合は、自分の声で録音してもOK。実際に口に出すことで、発音とスペルが結びつき、記憶が定着します。
また、カードを使うときは“表を見て言う→裏を見て確認”の流れで、必ず口に出して読み上げましょう。声に出すことで、脳内の「運動記憶」と「聴覚記憶」が同時に働き、忘れにくくなります。
ポイントは、「書くカード」ではなく「使うカード」を作ること。
作業ではなく、学びの道具として設計することで、1枚1枚のカードが“思い出せる知識”に変わります。
紙とアプリ、どちらが覚えやすい?
英単語カードの学習は、「紙かアプリか」を選ぶのではなく、場面に応じて使い分けるのが最も効果的です。
どちらにも得意分野があり、それぞれを補い合うことで、記憶の定着力が一気に高まります。
紙のカード:理解を深める「集中型ツール」
紙の英単語カードは、手を動かしながら学べる“集中学習”に最適です。
書く・読む・声に出す動作を通じて、単語の形・意味・発音を同時に記憶できます。
また、並べて眺めたり、順番を変えたりといった自由度があり、
「まとめて復習したい」「一気に整理したい」場面に強いのが特徴です。
たとえば、
- 放課後や夜の勉強時間に、机の上でカードを広げて“がっつり復習”
- 手書きしながら意味や例文を確認し、理解を深める
といった使い方がおすすめです。
アプリ:スキマ時間で続けられる「反復型ツール」
一方、アプリ型カードはスマホ1つで手軽に開けるため、忙しい人でも習慣化しやすいのが魅力。
自動シャッフル・音声再生・SRS(間隔反復)など、紙では難しい機能を備えています。
忘れかけたタイミングで出題してくれるため、「覚えたのに忘れる」を防ぐ仕組みが整っています。
たとえば、
- 電車やバスの中で、TANZAMなどのアプリを開いて5分間だけ復習
- 寝る前に苦手単語をAIが自動抽出して再確認
- 音声で発音チェックしながらリスニング力も強化
といった形で、いつでもどこでも復習が可能です。
ベストな組み合わせ:紙で理解 → アプリで定着
理想的なのは、家では紙で理解を深め、移動中はアプリで反復するという二段構え。
たとえば、
- 家で手書きカードを使って10単語を学ぶ(理解)
- 通学中にTANZAMで同じ単語を音声付きで復習(定着)
この流れを続けるだけで、「わかったつもり」が「使える知識」に変わります。
紙で“頭に入れる”、アプリで“忘れないように呼び戻す”。
それが、時間をムダにしない最強の英単語カード学習法です。
覚え方のコツ|作るだけで終わらせないために
英単語カードは「作ること」よりも「回すこと」が大事です。
きれいに作って満足してしまう人が多いですが、記憶は“繰り返し使う”ことでしか定着しません。
以下の3つを意識するだけで、単語カードが本当に使えるツールに変わります。
毎日“高速で回す”
カードは1枚ずつ丁寧に見るよりも、テンポよくめくっていくのが効果的です。
1日10〜15分で構わないので、覚えたかどうかを瞬時に判断しながらテンポよく回す習慣をつけましょう。
迷ったり止まったりする時間を減らすと、集中力が途切れず記憶の定着も早くなります。
間違えたカードだけ“集中復習”
全てを同じように繰り返すのは非効率です。
1回の復習で間違えた単語、曖昧だった単語だけを別の束に分けておきましょう。
次の日はその“苦手束”だけを重点的に回す。
これを続けると、自然と弱点が減っていき、得意な単語は定着していく流れができます。
「覚えたつもり」も数日後にもう一度
一度正解した単語も、数日後には忘れていることが多いです。
“完璧だと思った単語ほど、後日もう一度”が鉄則。
3日後・1週間後に再確認するだけで、記憶が長期化します。
復習タイミングの管理はアプリに任せてもOK
紙のカードだと、いつ・どの単語を復習すべきかを自分で考えるのが大変です。
その点、TANZAMのようなSRS(間隔反復)アプリなら、忘れかけたタイミングを自動で出題。
「作業なし」で同じ効果を得られるので、忙しい人やスケジュール管理が苦手な人にとって理想的なツールです。
要するに、「作る」で終わらせず、毎日回す・苦手を潰す・数日後に確認する。
この3ステップを守るだけで、英単語カードは“作業”から“成果”へと変わります。
TANZAMで「作らない単語カード学習」へ

英単語カードは本来、“作る”よりも“使って覚える”ことに時間をかけるべきです。
TANZAMは、そんな理想を実現するために生まれた「作らない単語カード学習」アプリです。
TANZAMなら、カード作りの手間がゼロ
従来の紙カード学習では、単語を書き出したり、意味を調べたりと、準備に時間がかかってしまいます。
TANZAMでは、例文・音声・イラストがすべて自動でセットされており、入力作業は一切不要。
そのまま“見る→思い出す→聞く”の流れに集中できます。
手書きの良さ × デジタルの効率を両立
手で覚える感覚を大切にしながら、アプリならではの機能も活かせるのがTANZAMの強みです。
紙のように1枚ずつ確認しつつ、シャッフル再生・音声発音・スワイプ操作でテンポよく復習できます。
「感覚」と「効率」、両方を兼ね備えた学習体験が可能です。
苦手単語も復習タイミングも自動で最適化
人間は、忘れかけた頃に復習することで記憶が定着します。
TANZAMのSRS(間隔反復)機能は、あなたの正答・誤答の記録から“忘れそうな単語”を自動で再出題。
苦手な単語は集中的に、得意な単語は間隔を空けて出すことで、
無理なく長期記憶へと定着させます。
“作る時間”を“使う時間”に
カードを作る時間が1日30分なら、1か月で15時間以上。
その時間をすべて「思い出す」「使う」学習に回せば、英単語の定着スピードは確実に上がります。
TANZAMは、作業を手放して記憶に集中できる、新しい形の単語カードです。
よくある質問(FAQ)
Q1. カードは何枚くらい作ればいい?
最初は50枚以内に絞るのがおすすめです。
一気に作りすぎると管理が大変になり、復習リズムが崩れやすくなります。
覚えたカードは別の束に差し替え、新しい単語を追加する“循環型”にすると、常に集中して取り組めます。
Q2. 書くのが面倒…本当に効果あるの?
はい、あります。
書くという動作は、脳の運動野を刺激し、意味記憶と結びつける効果があります。
1回でもいいので、自分の手でカードを書いてみましょう。
その後は、アプリで反復練習に切り替えれば、手書きの記憶と効率学習を両立できます。
Q3. アプリだけでも大丈夫?
もちろんOKです。
特にSRS(間隔反復)を搭載したアプリなら、紙カード以上に効率的に記憶が定着します。
TANZAMのようなアプリを使えば、自動で復習間隔を調整し、忘れる前に単語を出題してくれるため、時間をかけずに確実に覚えられます。
終わりに
カードでもアプリでも大切なのは、「続けられる仕組み」を作ること。
あなたの性格や生活リズムに合った方法を選び、毎日少しずつ積み重ねていきましょう。
単語カードは、作り方や使い方を少し変えるだけで、記憶の定着率が驚くほど変わります。
大切なのは、“完璧に作ること”ではなく、毎日カードを回して、少しずつ思い出せる単語を増やしていくこと。
忘れても大丈夫。人は忘れる生き物だからこそ、何度も触れる仕組みを作ることが大事です。
紙でもアプリでも、自分が「続けやすい」と思える方法で進めれば、それが最短ルートになります。
もし、「作る時間がない」「復習タイミングを管理できない」と感じたら、TANZAMのような“作らない単語カード”で始めてみてください。
音声・文脈・間隔反復のすべてを自動でこなしてくれるから、あなたは“覚えること”だけに集中できます。
今日の10分が、明日の“使える英語力”につながります。
無理なく、でも確実に。あなたのペースで積み重ねていきましょう。