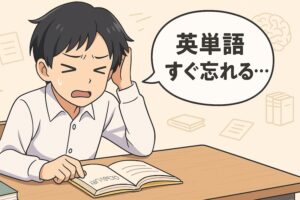小学生の英単語の覚え方|楽しく・続く・定着する学習法とは?

「英語、楽しくやってるみたいだけど…単語が全然覚えられなくて心配」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
今や小学生から英語に取り組むのが当たり前の時代。
でも、“英単語”となると、まだまだハードルが高いのが現実です。
単語は、意味のない「暗記」に見えてしまうと、たちまち苦手意識につながります。
逆に、ちょっとした工夫で「イメージ」と結びつけたり、遊びのように覚えられるようになると、グッと楽になります。
この記事では、そんな単語学習の最初の壁を乗り越えるために、「楽しく・定着する・続けやすい」 小学生向けの覚え方を紹介します。
お子さんが「英語、楽しい!」と思えるきっかけづくりに、ぜひお役立てください。
小学生の英単語学習がうまくいかない理由
「何度書いても覚えられない」「英語の授業でついていけてない気がする」──
そんな風に感じているお子さん、実は少なくありません。
小学生が英単語の学習でつまずく背景には、いくつか共通するポイントがあります。
抽象的な単語の意味がイメージできない
たとえば hope(希望) や idea(考え) といった単語。
大人にはなじみのある言葉でも、小学生には「なんとなくわかるけど、説明できない」「よく分からないまま覚えさせられている」と感じていることも。
意味が“体験”とつながっていないと、記憶に残りづらいのです。
書くだけ・読むだけの学習が単調すぎる
「ノートに何回も書いて」「声に出して読んで」──
こうした反復は一見よさそうに思えますが、興味を持ちづらい子にとっては苦痛の時間になりがちです。
単調さが原因で、そもそも机に向かいたくなくなるケースもよくあります。
意味とスペルの結びつきが弱く、すぐに忘れる
「昨日は言えたのに、今日はもう忘れてる…」という経験は多くの親子が通る道。
それは子どもの記憶力が悪いわけではなく、インプットの方法に問題があることがほとんどです。
意味・スペル・音のつながりを意識しないと、記憶は短期で消えていってしまいます。
成果が見えづらく、モチベーションが保てない
がんばっても「できた!」という実感が持てなければ、続けるのは難しくなります。
点数やスコアだけで評価されると、自己肯定感が下がってしまう子もいます。
✔ 大事なのは「合う方法」を見つけること
覚えられないのは、お子さんのせいではありません。
その子の性格や成長段階に合った“楽しく、定着しやすい学び方”を選ぶことが、英語との前向きな関係づくりの第一歩です。
次のセクションでは、実際にどんな方法が「続く・覚えられる」学び方なのか、わかりやすくご紹介していきます。
小学生におすすめの英単語の覚え方
「うちの子、英語に苦手意識があるみたい…」
そんなときは、“覚え方”そのものを少し変えてあげるだけで、驚くほど前向きになります。
ここでは、日常に取り入れやすく、記憶にしっかり残る5つの方法をご紹介します。
イラスト+音声で「イメージごと覚える」
子どもは、「文字」より「絵や音」に反応します。
たとえば、"dog" という単語に「ワンちゃんの絵」+「ドッグという発音」がついていると、「犬=dog=ワンワン」という三点が一気につながります。
取り入れ方の例:
- スマホアプリ(TANZAMなど)でイラストと音声つき単語を再生しながら一緒に発音してみる
- 紙の単語カードに「簡単な絵」を描いて、ミニお絵描き単語帳を親子で作る
- 「dog! ワンワンいたね!」と、散歩中に実物を見つけて口に出すのも効果的
フラッシュカードで「ゲーム感覚」に
書かせるより、遊ばせる。
テンポよくめくるだけのフラッシュカードは、子どもにとって“ゲーム”です。
取り入れ方の例:
- 「カード見せて3秒以内に答える」タイムチャレンジ
- 1枚ずつ見せて「スペルを当てたら1ポイント!」のごほうび制
- 「ママが言う日本語に対応する英語を探してめくってね」など、クイズ形式にするだけで集中力アップ
日常生活とリンクさせて「使う習慣」をつける
机の上よりも、生活の中の方が記憶に残りやすい。
見つけたとき・使う場面があるときに、「これ英語でなんて言うんだっけ?」を親子で確認するだけで学習になります。
取り入れ方の例:
- 「ごはんの前に ‘Let's eat!’ って言ってみようか!」
- 冷蔵庫に貼った「milk」「egg」の英単語カードを毎日声に出す
- 公園で “tree” や “bird” を見つけて、英語で呼び合う遊びにする
五感(見る・聞く・書く・話す)をフル活用する
五感を使った学びは、記憶の定着を何倍にも高めてくれます。
とくに「耳と口」を積極的に使うのがポイントです。
取り入れ方の例:
- 英単語を耳で聞きながら、声に出して真似する(シャドーイング)
- ノートに英単語を1回書いたら、必ず口に出す
- 単語のあとに “I like ~” など簡単な文をつけて、会話練習のように話してみる
親子で遊びながら「続く仕組み」をつくる
「勉強しなさい」ではなく、「ちょっと英語で遊ぼう」がベスト。
笑いながら学んだ単語は、忘れにくいです。
取り入れ方の例:
- 英単語しりとり(例:apple → elephant → tiger…)
- 英語で○×クイズを出し合う(例:"Is banana red?" → "No!")
- タイマー1分チャレンジ:「知ってる単語を何個言えるか競争!」
親子で“英語タイム”を楽しもう
英単語の学びは、「楽しさ × 習慣化」がすべて。
無理に机に向かわせるよりも、日常の中に少しだけ“英語で遊ぶ時間”を入れてあげることが、最大の学習効果につながります。
小学生の英単語学習を習慣化するコツ
「やらなきゃ」じゃなく「気づいたらやってる」状態に。
英単語の学習で一番の敵は、「続かないこと」。
でもそれは、子どもの努力不足ではなく、「習慣のつくり方」に原因があることがほとんどです。
ここでは、無理なく、自然と続けられる学習の仕組みをつくるためのコツをご紹介します。
1日5分 × 毎日のリズムに組み込む
「さあ英語の時間だよ」と切り出すより、生活の中に英語を“こっそり”差し込むのが続けるコツです。
やってみる例:
- 朝食後に「今日の1単語」を声に出す
- 歯磨き中にアプリで2語だけ聴く
- 寝る前にベッドでフラッシュカードを1セット
ポイントは、“タイミングを決めておく”こと。
毎日同じ流れの中で繰り返されると、脳も「これは習慣」と認識しやすくなります。
成長が見える“見える化”でモチベーションUP
子どもは、「できるようになった」が“目に見える”と、ぐんとやる気になります。
おすすめの見える化ツール:
- 覚えた単語にシールを貼る「単語マスター表」
- アプリで達成度を確認(TANZAMなど)
- 単語カードを「覚えた箱」「復習箱」に分けて進捗を実感させる
「がんばった分が目に見える=もっとやってみよう」に自然とつながります。
「できた単語」より「取り組み姿勢」を褒める
褒め方を少し変えるだけで、子どもの学習意欲はぐっと伸びます。
たとえばこんな声かけ:
- 「3日続けてやれたの、すごいね!」
- 「今日はすぐに始められたのがいいね」
- 「ちょっと難しい単語にもチャレンジしたの、かっこいいよ!」
結果より“プロセス”を認めることで、「やってよかった!」という気持ちが強化されます。
「わかるようになった!」の喜び体験をつくる
子どもが「英語って楽しい!」と感じるきっかけは、“できた!”の成功体験です。
成功体験のつくり方:
- 5個だけの“おさらいテスト”で満点を取らせてあげる
- 英単語しりとりで大人に勝たせてあげる
- 習った単語が絵本やYouTubeに出てきたら「覚えてたね!」と気づかせる
“わかった感”は、学習の最大のモチベーションです。
その体験を親が少しだけ意図的に演出してあげるだけで、自然と次もやりたくなります。
英語学習を続けるために大切なのは、子どもの根気や性格ではなく、「続けやすい仕組み」をどう用意するか。
1日5分でも、積み重ねればしっかり力になります。
無理なく、楽しく、ポジティブなサイクルを回していきましょう。
目的別|小学生におすすめの単語帳・教材
英単語の教材といっても種類はさまざま。
年齢や目的によって「合う・合わない」があるので、まずはお子さんの今の段階に合った教材を選ぶことが第一歩です。
以下の表は、よくある3つの目的別におすすめの教材と特徴をまとめたものです。
| 目的 | おすすめ教材 | 特徴 |
| 英検5級〜4級の受験対策 | 旺文社などの英検対策ドリル | 英検形式に特化/出題傾向に合わせた単語練習 |
| はじめての英単語習得 | 絵辞典(例:Oxford絵辞典)/TANZAM | イラスト・音声・例文付き/楽しみながら覚えられる |
| 中学英語の準備 | 中学英語の先取り教材(例:ニュークラウン準拠) | 文法と連動/中学入学前の土台づくりに◎ |
英検5級〜4級を目指すなら:出題傾向に沿った「対策本」
英検を目標にしているなら、英検用に作られた教材を使うのがいちばんの近道です。
- 旺文社やアスク出版などが定番
- リスニング/単語/会話表現などが試験形式で学べる
- 本番の雰囲気になれる「模試」付きの教材もおすすめ
ポイント:
試験前だけでなく、毎日の勉強習慣に少しずつ取り入れることがスコアアップにつながります。
英語がはじめての子には:絵辞典やTANZAMで“楽しく入り口づくり”
単語学習が初めての小学生には、「覚えるぞ!」というより“遊びながら触れる”感覚が大切です。
- 絵辞典(Oxford Picture Dictionaryなど):絵と一緒に単語を覚えられる
- TANZAM:イラスト+音声+例文で、五感を使った記憶定着ができるアプリ
ポイント:
最初に「楽しい」「意味がわかる」という感覚を持てると、その後の学習意欲が自然と高まります。
中学英語の先取りには:文法と一緒に覚える教材を
「中学でつまずきたくない」「少し先取りしておきたい」という場合には、中学英語の土台をやさしく学べる教材がぴったりです。
- 中学英語準拠の単語帳(例:「中学英語を先取り」シリーズ)
- 「be動詞」「一般動詞」など文法の流れと一緒に単語が出てくる構成
ポイント:
単語だけでなく「文でどう使われるか」まで学ぶことで、“意味のある語彙力”が育ちます。
どれが正解というよりも、お子さんの現在地にぴったり合う教材かどうかが大事。
- 英語に慣れる段階 → 絵辞典/TANZAM
- 目的がある → 英検対策ドリル
- 先取りしたい → 中学準拠の教材
その上で、「子どもが手に取りたくなる・続けやすい」と感じるかどうかも、教材選びの大事なポイントです。
TANZAMならではの学びやすさ
小学生の英単語学習で一番むずかしいのは、「楽しく続けて、しっかり身につけること」。
TANZAM(タンザム)は、子どもが“使いたくなる設計”と、記憶に残る仕掛けが詰まった英単語アプリです。
親子での学習にも自然になじみ、無理なく習慣化できます。
絵・音声・例文で “意味ごと覚える”
「apple=りんご」だけではなく、絵を見て、音を聞いて、“文でどう使うか”まで自然にわかるのがTANZAMの特徴です。
- イラスト:単語の意味が直感的に入る
- 音声:発音も耳からインプット
- 例文:単語だけでなく“使える英語”として身につく
単語の丸暗記ではなく、「あ、こういうときに使う言葉なんだ」と実感しながら覚えることができます。
自動復習で“忘れにくいサイクル”が完成
覚えてもすぐ忘れてしまう——小学生あるあるです。
TANZAMでは、学習履歴に応じて復習のタイミングを自動で調整してくれるので、「忘れたころに、ちょうどいい復習」ができます。
- 覚えた単語は間隔を空けて出題
- 苦手な単語は、くり返し登場
- 「記憶に残るサイクル」がアプリで自動化
忙しい保護者が「復習の計画」を立てなくても、自然と効果的な反復学習ができるのも安心ポイントです。
「覚える」から「わかる」へ。続けたくなる学びの仕掛け
英語は“暗記するもの”と思われがちですが、TANZAMでは「意味がわかるから覚えられる」学び方を大切にしています。
TANZAMの特徴は、ただイラストを眺めるだけではありません。
- 単語に対応したイラストでイメージがパッと浮かぶ
- シンプルな例文で「どんな場面で使うのか」がつかめる
- 音声つきだから、発音とリズムも自然に身につく
この3つが組み合わさることで、「見て」「聞いて」「使って」覚えるスタイルが自然と日常に根づいていきます。
さらに、毎日の学習記録や達成表示も自動で反映されるので、「ここまでやった!」が目に見えてわかるのも嬉しいポイント。
「単語って楽しいかも」と思えたら、それが第一歩。
TANZAMは、英語が“自分の言葉”になっていく感覚を育てるアプリです。親子で一緒に、まずは1日3分から始めてみてください。
まとめ|小学生に必要なのは「楽しい × 定着する」英単語学習
「うちの子、英単語が全然覚えられなくて…」
そんな悩みの背景には、単語が「意味のない記号」のように見えていることが多くあります。
大切なのは、“暗記”ではなく、“イメージできる・使える単語”に変えること。
- 単語の意味をイラストや音で直感的に理解する
- 文の中でどんな風に使われるかを知る
- 自分の生活とつながる形で覚える
そんな「楽しく、身につく」学び方が、子どもたちの英語力の土台になります。
まずは1日5分、親子で楽しく
大がかりな準備は不要です。
朝の準備中や、寝る前の5分からスタートすれば十分。
- 今日はこの単語をイラストで言ってみよう
- 音を聞いてマネしてみよう
- 生活の中で見つけてみよう(例:fridge=冷蔵庫)
そんな「一緒に楽しむ工夫」こそが、英語を好きになる第一歩。
小学生のうちは、学力よりも「学ぶことが楽しい」と思える気持ちが何より大事です。
習慣にすれば、英語は“苦手”ではなく“得意”になる
小さな一歩の積み重ねが、将来の語学力を大きく左右します。
TANZAMのようなアプリや教材をうまく活用して、
「毎日ちょっとずつ、でも確実に身につく」学習スタイルを、ぜひ親子で見つけていきましょう。